しみん基金・KOBE | 助成先団体の事業成果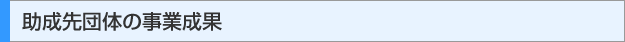
2023年度助成先団体の成果報告
2024年12月10日に兵庫県中央労働センターで、成果報告会を実施しました。今年は24年度の助成事業を顕彰事業に変更していたので、顕彰事業の入賞提案への贈呈式、黒田裕子賞贈呈式も併せて行う、もり沢山な会となり、33名の方のご参加と多くのマスコミが来られました。
助成先団体の事業成果とメッセージ ~ご寄付はこのように活用されました
一般枠
| 1 | (特活)全国夜間中学ネット(特定非営利活動法人Seeds of Tomorrowに名称変更) | 神戸市須磨区 |
|---|---|---|
| 事業名 | 学習支援塾 みんラボ 長田・甲南 | |
| 事業の 成果 |
 事業展開が2か所になって生徒数が増加し各地区に学習支援の取り組みが浸透してきた。指導の中で改めて現在の中学生の学力格差を感じたが、学び直す過程で多くの生徒が成績を上げることができ、自尊感情が生まれ自ら勉強する習慣が身についた。現在の学校システムに一石を投じるものと考える。 事業展開が2か所になって生徒数が増加し各地区に学習支援の取り組みが浸透してきた。指導の中で改めて現在の中学生の学力格差を感じたが、学び直す過程で多くの生徒が成績を上げることができ、自尊感情が生まれ自ら勉強する習慣が身についた。現在の学校システムに一石を投じるものと考える。
|
|
| メッセージ | 私たちの目標である、各中学校区に1か所の学習支援教室を設置し教育システムとして制度化することについて、他団体との交流研修で活動の方針や組織強化の方法など多くの刺激や勉強があった。学生ボランティアも視野や世界観が広がり、活動を通して成長している姿が見てとれる。 | |
| 2 | (特活)ミャンマーKOBE | 神戸市長田区 |
|---|---|---|
| 事業名 | 急増するミャンマー人への支援強化と、自らの課題解決 活動の支援 | |
| 事業の 成果 |
 建物の補修により1階事務所は生活相談の常時受付や食料等の備蓄が可能になり、2階にはミャンマー人留学生が入居できた。早速目的にかなうスタートになった。
ミャンマー人の文化的側面へのバックアップができ信頼関係は徐々に進んでいる。特にメリケンパークで開催した「水かけ祭」には1000人近くの参加者があり大きな自信になった。 建物の補修により1階事務所は生活相談の常時受付や食料等の備蓄が可能になり、2階にはミャンマー人留学生が入居できた。早速目的にかなうスタートになった。
ミャンマー人の文化的側面へのバックアップができ信頼関係は徐々に進んでいる。特にメリケンパークで開催した「水かけ祭」には1000人近くの参加者があり大きな自信になった。
|
|
| メッセージ | 初めて本格的な「水かけ祭」を行うことになったが、幸い寄付も集まり小雨の中多くのミャンマー人の参加を得て成功裏に終えることができた。ミャンマー人たちが生き生きとふるまう様子に感動し、苦労してやってよかったと胸をなでおろした。 | |
| 3 | たらぶ準備会(特定非営利活動法人陽だまりの会の事業として実施) | 神戸市東灘区 |
|---|---|---|
| 事業名 | 孤独・孤立対策支援活動事業 ―ひきこもり(特に 8050 問題、就職氷河期世代など喫緊の課題に対処するため)に特化したプラットフォームを基盤とした伴走型支援活動― | |
| 事業の 成果 |
 生きづらさを抱えた方の支援として、プラットフォーム(多職種連携)を基盤にした伴走型支援を中心に、啓発・啓蒙活動を各種団体、個人、各支援団体に継続して行った。組織活性化のための規約変更を行い、体制を整えたが当初の目的に達することはできず陽だまりの会の1プロジェクトとして活動をしていくこととした。 生きづらさを抱えた方の支援として、プラットフォーム(多職種連携)を基盤にした伴走型支援を中心に、啓発・啓蒙活動を各種団体、個人、各支援団体に継続して行った。組織活性化のための規約変更を行い、体制を整えたが当初の目的に達することはできず陽だまりの会の1プロジェクトとして活動をしていくこととした。
|
|
| メッセージ | 現在ひきこもり支援については流動期にきており、今後とも伴走型支援が必要とされることを念頭に活動をしたい。そのためにも活動を通じて当団体の認知度向上と活動の普及ができるように励んでいきたい。 | |
| 4 | 面会交流支援センターピロティ | 神戸市中央区 |
|---|---|---|
| 事業名 | 子どもの利益となる面会交流等の支援事業 | |
| 事業の 成果 |
 両親の葛藤により会えなかった子どもが別居親と楽しい時間を過ごせた。安心感や自己肯定感などが子どもの人生に寄与する精神的支えになり意義ある活動になった。
ACCSJ認証(面会交流支援全国協会による認証)を全国で7番目に取得した。子どもの健全な成長発達への貢献、他の面会交流支援団体との交流や横の連携が大きな成果である。 両親の葛藤により会えなかった子どもが別居親と楽しい時間を過ごせた。安心感や自己肯定感などが子どもの人生に寄与する精神的支えになり意義ある活動になった。
ACCSJ認証(面会交流支援全国協会による認証)を全国で7番目に取得した。子どもの健全な成長発達への貢献、他の面会交流支援団体との交流や横の連携が大きな成果である。
|
|
| メッセージ | 私たちは形式的な親子面会ではなく、子どもの発達段階や親子の状況に応じて丁寧に関わっているため、活動継続には苦慮している面もある。助成により支援人員の増員や研修も実施できた。新たな認証も受けて、引き続き子どもたちが安心できる環境と支援の質の向上に努めながら活動していきたい。 | |
| 5 | 多文化共生センターひょうご | 神戸市東灘区 |
|---|---|---|
| 事業名 | 多文化・多世代の顔がみえるまちづくり | |
| 事業の 成果 |
 異なる趣旨の行事に参画したことで他事業でも協力関係が得られ収益につながった。イベント運営のノウハウを共有して横展開ができた。特に「ふかえ大敬老会」は多様な文化、価値観を可視化できた。次代の担い手として小学生が成長して高校生ボランティアになったり親子二代で参画する例があり、事業の継続が期待できる。 異なる趣旨の行事に参画したことで他事業でも協力関係が得られ収益につながった。イベント運営のノウハウを共有して横展開ができた。特に「ふかえ大敬老会」は多様な文化、価値観を可視化できた。次代の担い手として小学生が成長して高校生ボランティアになったり親子二代で参画する例があり、事業の継続が期待できる。
|
|
| メッセージ | 「ふかえ大敬老会」では多文化に関心の低い高齢者が外国人の参加を歓迎するという変化が見られ、その後地域の外国人が高齢者の生活支援をする活動も具体化し、全国でも類を見ない例だと期待している。会場変更を強いられた「多文化フェスティバル深江」が無事開催できたのは地域のキーパーソンの働きが大きかった。 | |
| 6 | 「まちの本屋」上映実行委員会/a> | 芦屋市 |
|---|---|---|
| 事業名 | ドキュメンタリー映画まちの本屋上映会等の実施 | |
| 事業の 成果 |
 上映会は一人の小学生の思いから始まり、映画製作の関係者が登壇するトークライブも開催し、実行委員の小学生らにも成し遂げた大きな自信が生まれた。次代を担う子どもや多くの世代に、生きることや仕事に対する姿勢、地域のつながりの大切さに気づくきっかけを伝えた。多くの協賛、後援、助成により次回上映が検討できる状況になった。 上映会は一人の小学生の思いから始まり、映画製作の関係者が登壇するトークライブも開催し、実行委員の小学生らにも成し遂げた大きな自信が生まれた。次代を担う子どもや多くの世代に、生きることや仕事に対する姿勢、地域のつながりの大切さに気づくきっかけを伝えた。多くの協賛、後援、助成により次回上映が検討できる状況になった。
|
|
| メッセージ | 実行委員の小学生から「準備が大変」「当日は緊張した」「また何かやってみたい」という声があった。学業や仕事の傍らイベントを実施・継続するためには、家族や関係者の協力、効率化の工夫が欠かせないと感じる。来場者の感想や意見が励みになり次回に活かしたいと考えている。 | |
特定枠
| 7 | あすパ・ユース震災語り部隊 | 神戸市灘区 |
|---|---|---|
| 事業名 | 灘区成徳地区における、若者による震災の伝承活動 | |
| 事業の 成果 |
 成徳地域での定例活動により、若者(高校生・大学生・専門学校生)が住民から直接震災経験を聞き取ることができ、自分の言葉で語り部を始めた。聞き取りやカフェ企画で高齢者との交流が進み地域に当団体が受け入れられた。東日本大震災の被災地訪問では、現地で活動する若者と交流し今後の活動に前向きに取り組むことにつながった。 成徳地域での定例活動により、若者(高校生・大学生・専門学校生)が住民から直接震災経験を聞き取ることができ、自分の言葉で語り部を始めた。聞き取りやカフェ企画で高齢者との交流が進み地域に当団体が受け入れられた。東日本大震災の被災地訪問では、現地で活動する若者と交流し今後の活動に前向きに取り組むことにつながった。
|
|
| メッセージ | 宮城での合宿参加は普段の活動を大局的に見るきっかけとなり、全体を通して災害からの学びを伝えていくことに大きな視点を持つことができた。これらは若者が学校の枠を超えて活動することで得られたものである。 今後も若者が視野を広げるきっかけとなる活動、震災の学びを次世代に伝える活動、灘区成徳地域において世代間の学び合いを促進する活動を続けていきたい。 | |

